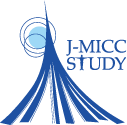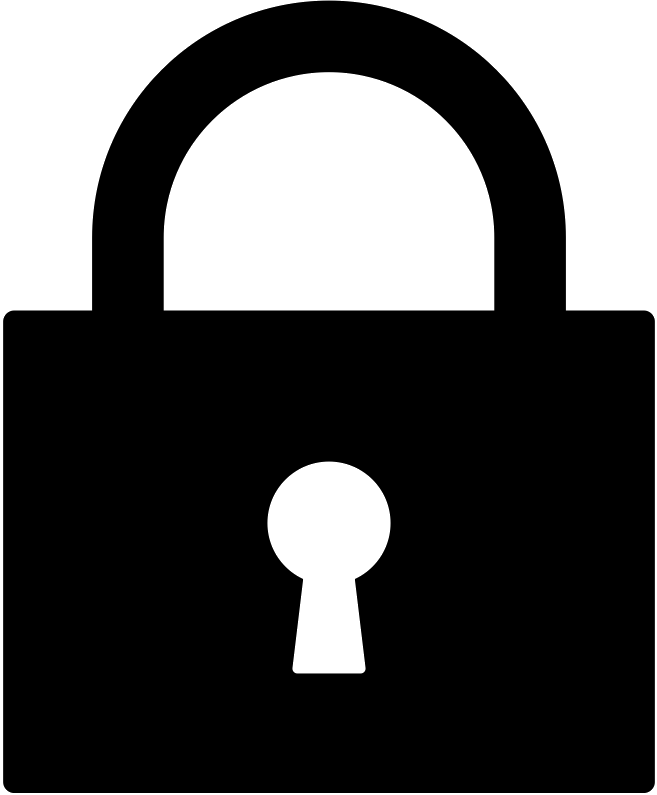富永 祐民氏(愛知県がんセンター名誉総長/あいち健康の森健康科学総合センター名誉センター長/日本癌学会名誉会員/日本がん予防学会理事長)

今回は、わが国の疫学研究・予防医学の先達であり、主に循環器やがんの疫学に長く取り組んできた富永祐民先生にご登場いただきます。近年、日本でも多くの大規模疫学研究が行われるようになりましたが、富永先生はその礎を築いた研究者であり、まさにフロントランナーのお一人です。2015年3月まで、J-MICC研究の外部評価委員会委員長も務められました。ご自身の疫学研究者としての歩みと重ね合わせながら、J-MICC研究および日本の大規模分子疫学コーホート研究への期待について伺いました。
(取材日:2015年12月10日)
肝がんの疫学研究に取り組む過程で
胆道がんと肝がんの地理分布が異なることを発見
- 先生が疫学研究に携わるようになった経緯を教えてください
-
富永氏 私は1962年に大阪大学医学部を卒業しましたが、医学部の学生の頃から肝がんや肝硬変などの難治性肝疾患に興味を持っていました。しかし、早期診断も治療も困難で、ベッドサイドで診ている患者さんがみな亡くなってしまうのです。当時の『外科研究の進歩』という雑誌に世界各地で行われた肝がん手術例の治療成績のレビューが掲載されましたが、数十例の全例が1年以内に死亡していました。一方、1963年4月に大阪で第16回日本医学会総会が開催され、大阪大学医学部病理学の宮地徹教授が「日本人の肝がんの特徴」と題した特別講演を行いました。そこで、世界的に見ると肝がんは東南アジアやアフリカなど栄養が悪い地域に多発しており、栄養改善によって予防しうる可能性が示唆されました。私は「治療がダメなら予防へ」と考え、予防医学の道へ進むことにしたのです。
- どういった方向で研究を進められたのですか
-
富永氏 インターンを終わって大学院へ進み、公衆衛生の循環器疾患グループに入りました。栄養面を担当したのですが、聞き取り調査などは不正確なので血液で栄養診断をしようと考えたのです。そこで、多数の住民や企業従業員を対象として血清タンパクや血清コレステロール、中性脂肪を測定し、循環器疾患との関連を調べました。結論から言うと、血液で集団としての栄養診断は十分に可能だということがわかりました。大学院修了後はアメリカへ留学し、心筋梗塞患者に対するコレステロール低下薬による大規模な長期介入試験に関与し、帰国後は環境庁で公害健康被害補償法を立ち上げるプロジェクトなどに参画しました。
- その後、がんの疫学に携わることになるわけですね
-
富永氏 回り道をしましたが、1977年に愛知県がんセンター研究所疫学部に赴任し、当初の目的であった肝がんの疫学研究を始めました。まず、日本国内の肝がん多発地域を見つけようと考え、人口動態統計を用いて市郡別の肝がん地図を作成しました。そこから偶然、驚くべき結果が得られたのです。当時は死因が国際疾病分類第6版(ICD-6)で分類されており、肝がんと胆道がんが「肝胆がん」として同じ項目に分類されていましたので、別々に調べ直したところ、胆道がんと肝がんの地理分布がまったく異なることを発見したのです。その結果をただちに日本癌学会で報告しました。さらに、胆道がんの世界の地理分布も調べ、日本人の胆道がん死亡率が世界的に見て高率であることがわかったのです。その後、胆道がんが最も多いのは新潟県であることを知り、新潟県立がんセンターと協力して原因究明のための症例―対照研究を行いました。そして、一部の胆道がんには、胆管に寄生する肝吸虫の関与している可能性を明らかにしました。
このように、疫学研究では偶然から新事実が発見されることも少なくありません。疫学者には、しっかりとした知識をベースとして、予想外の事象を見逃さないセンスが求められるのではないかと思います。
疫学研究の最終目的は予防であり、
疫学を「集団予防医学」と定義すべき
- 疫学研究の意義をどうお考えですか
-
富永氏 まず、「疫学」という言葉の指す対象が非常に曖昧で、一般の人にはわかりにくい面が1あります。もともとは流行り病である疫病の原因を探るものでした。しかし、その方法論を循環器やがんなどにも応用し、その定義が広くなっている現在、疫学研究というよりも「予防研究」という言葉がふさわしいのではないかと思っています。
疫学的な研究方法はいろいろありますが、疾患のリスク要因を解明するための「分析疫学」で原因または予防因子を見つけることができれば、原因を取り除き、予防因子を補充することにより疾患の予防が可能になります。つまり、疫学の最終目標は疾患の予防であると言えます。また、「記述疫学」も疾患の頻度の把握と予防対策を行った場合の予防効果の評価に役立つので、予防に密接に関連しています。こうした考えから、愛知県がんセンター研究所長を務めていたときに、疫学部を「疫学予防部」に名称を変更しました。また、1996年に名古屋で日本疫学会を開催しましたが、そのときのスローガンを“疫学から予防へ”としました。疫学の定義はさまざまであり、アメリカでも混乱していましたが、私は疫学を「集団予防医学」と定義し、予防というキーワードを強調したほうが国民の理解もより得られるのではないかと思います。
- これまで疫学研究に携わってきて印象に残っていることは何ですか
-
富永氏 2つあります。1つは、前述したアメリカ留学時に、全米8,341名の心筋梗塞患者に対する5種類のコレステロール低下薬の二次予防効果を評価する大規模な介入試験に従事したことです。当時、アメリカでは心筋梗塞が死因第1位になっており、NIH主導の国家プロジェクトとして多額の予算を割いて行われた研究でした。結果的にプラセボと比較して5種類の脂質異常改善薬の延命効果の優位性は実証されず驚きましたが、その仕事は非常に興味深く、やり甲斐のあるものでした。アメリカでは6年半にわたってon the job trainingで臨床試験の方法論を学びました。そして、帰国の1970年代後半にCOX比例ハザードモデルを日本で初めて実際に臨床例に応用しました。1980年には『治療効果判定のための実用統計学——生命表法の解説』(蟹書房)という単行本を発刊するとともに、日本臨床腫瘍研究グループ(JCOG)などに参加して臨床試験のデザインの改善に貢献したことも心に残っています。

もう1つは、主に環境庁で大気汚染の健康影響に関する疫学研究に従事したことです。通常の疫学研究では原因のわからない疾患の原因を究明しますが、大気汚染の場合、原因は明らかで、その原因が健康にどのように、どの程度影響するかという量—反応関係を調べました。研究の結果、大気汚染と肺気腫や気管支喘息などの慢性閉塞性肺疾患との因果関係は疫学的に確認できましたが、肺がんとの関係ははっきりしませんでした。そこで、環境庁を辞めて愛知県がんセンター研究所へ移ってから、大気汚染と肺がんの関係を調べるための研究に着手しました。当時地域がん登録のあった宮城県、愛知県、大阪府の3府県の行政と研究者の協力を得て、都市部・農村部の40歳以上の地域住民約10万人を対象とした長期間にわたるコーホート研究を実施したのです。1983年に研究を開始して15年間以上追跡した結果、2005年頃に浮遊粒子状物質(SPM)による大気汚染と肺がんの因果関係が証明されました。この調査結果は2009年に定められたPM2.5の環境基準の基礎データとして使われました。その年、環境大臣表彰を受け、長年にわたる地味な苦労が報われたような気がしたものです。
- 疫学研究の魅力は何ですか
-
富永氏 疫学研究による原因究明は宝探しや探検に通じるものがあります。ちなみに、国立がんセンター疫学部長を務め、喫煙とがんとの相関関係を解明した故・平山雄先生は、かつて毎日新聞に自分が経験したがんの疫学研究の結果を連載し、『がん謎解き旅』という単行本を発刊しました。私はよく疫学者は“ここ掘れワンワン”と言う。「宝がこのへんにありそうだ」という “容疑濃厚”という段階までは迫れるのですが、犯人の特定まではできません。決定的な原因究明は他の領域の研究を待たなければならないことが多いのです。例えば、SMONのキノフォルム、水俣病のメチル水銀、イタイイタイ病のカドミウム、成人T細胞白血病・リンパ腫の原因ウイルスのHTLV1などが良い例です。

部屋の窓からよく見ていた大きな楠。
こころ安らぐひとときだったそうだ。統計的な分析を行っても、その結果はあくまでも確率であり、リスク因子を確定することはできません。疫学研究では仮説が外れることも少なくありません。それでも、宝くじと同じように、当たったときの快感には何物にも変えがたい魅力があります。
また、臨床では一人ひとりの患者さんの診断・治療を行い、うまく治った場合には患者さんに感謝されて医師も満足します。しかし、疫学研究は集団としての診断と予防を行うので、個々の患者さんから感謝されることはありません。疫学研究に携わる人は、そこにやり甲斐を期待してはいけません。病気にかかる人が減ったことに対して、ひそかな満足を味わうにとどめるのです。
予防という最終目標に到達するため
軌道修正も恐れずに粘り強い取り組みを
- J-MICC研究および日本の大規模な分子疫学コーホート研究への期待と展望について伺います
-
富永氏 そもそもJ-MICC研究は個体差を考慮した個別予防を目的にしています。その目的を常に視野に入れておくことが重要です。
私が医学教育を受けた時代には、まだ分子生物学という分野はありませんでしたが、以前から不審に思っていたことがありました。その一つは、喫煙が肺がんのリスク因子であることは明らかであるにもかかわらず、一生涯喫煙を続けても、ヘビースモーカーであっても肺がんにかからない場合が多く、一部の喫煙者しか肺がんにかからないのはなぜかということです。喫煙していて肺がんにかかった人は、何らかの決定因子が働いて「かかるべくしてかかった」のか、確率論的に「偶然悪いくじを引いた」のかがわかりません。ゲノム研究により何らかの決定因子によって肺がんにかかることがわかれば、禁煙指導など予防に役立つと思います。
1973年にKellermanという研究者が、肺がん患者群と対照群のaryl hydrocarbon hydroxylase(AHH)活性を比較し、肺がん患者群の肺胞マクロファージのAHH活性が高いことを報告しました。AHHは、活性の低い多環炭化水素系発がん物質を不安定なDNAに結びつきやすいエポキシド状態に変換する誘導酵素ですが、支配する遺伝子は不明でした。
その後、喫煙により生じるタールに含まれる発がん物質の活性化に関与するチトクロームP450酵素群を支配するCYP1A1、CYP1A2、CYP2E1などの遺伝子に関する研究が進みました。その結果、とくにCYP1A1の遺伝子多型がAHH活性の誘導に関連することがわかり、CYP1A1がm2m2型の場合はリスクが高く、m1m1型の場合はリスクの低いことが明らかになりました。
このように、系統的なDNA配列多型に関するゲノム研究によって個別のがん発生リスクの予知が可能になり、個別のオーダーメイド予防が普及すれば予防効果と予防効率を改善できるようになると思います。また、がん検診についてもゲノム情報を考慮した個別化検診を目指すべきでしょう。
- J-MICC研究のような大規模コーホート研究を進める上で大切なことは何だとお考えですか
-
富永氏 がん発生リスクに関連する遺伝子を特定するという分子疫学コーホート研究の特長とねらいをはっきりさせた上で、貴重で膨大なデータを系統的に扱い、分母を大きくして解析できる研究システムを構築していく必要があると思います。また、データの解析については因果の逆転を避けるための工夫をし、がん死亡だけではなく全死亡をエンドポイントとして、total mortalityとリスクファクターとの関連を明らかにすることも重要でしょう。
疫学研究の最終目標はあくまでも疾患の予防です。研究者は枝葉の研究結果に一喜一憂するのではなく、木の幹である研究全体の最終目標を見失わないよう現在地点を常に意識しておかなければなりません。疫学研究には紆余曲折もあります。金星探査機「あかつき」のように軌道投入に失敗することもあるでしょう。しかし、目指すのはあくまでも金星です。最終目的地へ到達するために、ときには軌道修正も恐れず、粘り強く取り組むことが疫学研究者には求められるのではないかと思います。
- 最後に富永先生のご趣味を教えてください
-
富永氏 いろいろあります。まず屋根瓦の魔除けの鍾馗(しょうき)さんの写真撮影は半世紀にわたる趣味です。米国留学中に虜になったニューオーリーンズジャズを聴くことも大好き。そして陶芸です。約20年前に愛知県がんセンターが改築工事をした際には敷地内から出た粘土を使って湯飲み茶碗などを作りました。
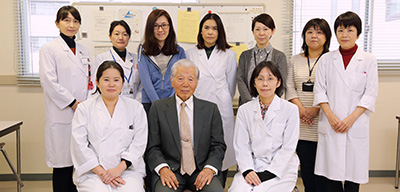
愛知県がんセンターJ-MICC研究に携わっているスタッフと共に。